日経POS情報導入事例

青山学院大学
青山学院大学様 日経POS情報サービス導入事例
購買データを活用した講義で
学生の実践的な思考力を養う

経営学部 マーケティング学科
教授 博士(工学)
橫山暁氏
マーケティングや商品開発、経営戦路などビジネスのあらゆる現場でデータに基づいて意思決定できる人材の重要性が増している。大学においても実践的なデータ教育が大きな課題となるなか、青山学院大学経営学部マーケティング学科の横山暁教授は「日経POS情報」から得たレシートデータなどを軸に据えた講義を展開している。生きたデータは、学生の学びにどのような化学反応を起こしているのだろうか。
■ご契約サービス:SCAN
■ご契約サービス:SCAN
導入の背景
身近なテーマ設定で、データ分析に苦手意識を持つ学生のハードルを下げる

ーーなぜ文系の学生が多いマーケティング学科の授業で、データ分析を積極的に取り入れようと考えたのでしょうか?
横山:従来のマーケティングは「KKD」、つまり勘・経験・度胸が重視される世界でしたが、今では蓄積したデータに基づいて客観的に判断する「データドリブン経営」が常識となりつつあります。これからの学生たちが経営やマーケティングでその能力を発揮するには、データリテラシー、つまりデータを正しく読み取り、解釈する力は不可欠となっているのです。幸い、私の専門であるデータ分析のスキルと、世の中や大学が求める「データに強い文系人材を育てたい」というニーズが合致し、日経POS情報のデータを活用した授業につながりました。
ーー数あるデータ教材から、なぜ日経POS情報を選んだのでしょうか。
横山:教育現場が抱える現実的な課題をいくつもクリアできる、総合的なバランスの良さがあるからです。研究用のデータは非常に高価なものが多いのですが、日経POS情報は大学の予算内で継続的に購入できる価格帯になっています。そのうえ取り扱っているカテゴリーが豊富で、その時々の学生の興味に沿ったカテゴリー単位での購入が可能です。例えば、最近では学生の興味関心を考慮して「エナジードリンク」のデータを新たに購入したり、逆に使用頻度が減った「水」のデータをやめたりといった調整を行っています。カテゴリー単位で継続的な購入もできるので、時系列の推移を見るうえでも有用です。最初のうちはデータ分析に苦手意識を持つ学生も結構いますから、取り扱うデータが学生の興味に合っていることで授業に関心を持ちやすくなります。
また、データ自体を切り出して学生たちのパソコンで扱える規模に調整できます。そのため初心者への導入から高度なマーケティング分析にまで幅広く対応することができます。これだけの条件を満たし、多くの学生が履修する授業で使えるデータは他にほとんどありません。大学での授業に対応できる実践的なデータ教材という意味では、日経POS情報が唯一の選択肢だったと考えています。
横山:従来のマーケティングは「KKD」、つまり勘・経験・度胸が重視される世界でしたが、今では蓄積したデータに基づいて客観的に判断する「データドリブン経営」が常識となりつつあります。これからの学生たちが経営やマーケティングでその能力を発揮するには、データリテラシー、つまりデータを正しく読み取り、解釈する力は不可欠となっているのです。幸い、私の専門であるデータ分析のスキルと、世の中や大学が求める「データに強い文系人材を育てたい」というニーズが合致し、日経POS情報のデータを活用した授業につながりました。
ーー数あるデータ教材から、なぜ日経POS情報を選んだのでしょうか。
横山:教育現場が抱える現実的な課題をいくつもクリアできる、総合的なバランスの良さがあるからです。研究用のデータは非常に高価なものが多いのですが、日経POS情報は大学の予算内で継続的に購入できる価格帯になっています。そのうえ取り扱っているカテゴリーが豊富で、その時々の学生の興味に沿ったカテゴリー単位での購入が可能です。例えば、最近では学生の興味関心を考慮して「エナジードリンク」のデータを新たに購入したり、逆に使用頻度が減った「水」のデータをやめたりといった調整を行っています。カテゴリー単位で継続的な購入もできるので、時系列の推移を見るうえでも有用です。最初のうちはデータ分析に苦手意識を持つ学生も結構いますから、取り扱うデータが学生の興味に合っていることで授業に関心を持ちやすくなります。
また、データ自体を切り出して学生たちのパソコンで扱える規模に調整できます。そのため初心者への導入から高度なマーケティング分析にまで幅広く対応することができます。これだけの条件を満たし、多くの学生が履修する授業で使えるデータは他にほとんどありません。大学での授業に対応できる実践的なデータ教材という意味では、日経POS情報が唯一の選択肢だったと考えています。
活用状況
データの種類や授業形式を変えて、入門から応用まで幅広い授業を展開

ー一横山先生の講義では、どのように日経POS情報を活用していますか。
横山:まだデータに触ったことのない1年生から、比較的高度な分析を行うゼミの演習まで、私の担当する多くの講義で日経POS情報を取り入れています。
まず1年生には、データ分析の基礎を学ぶ講義を必修科目として学んでもらっています。ここで基礎的なデータリテラシーを身に付け、慣れてきたら日経POS情報の購買データを使ったグループワークに臨みます。2年次に進むとProject-Based Learning (PBL:課題解決型学習)を取り入れた授業が始まります。ここでは週次集計データや、より高度な併売分析が可能なレシートデータなどをもとに、マーケティング的な観点から現状分析や課題解決を議論します。3年次でも継続してゼミの演習に日経POS情報を活用。さらに複数のゼミと共同で、日経POS情報を活用したデータ分析コンペも実施しています。これはデータを渡して50時間で分析しプレゼン資料を作成するというトライアルで、スキルを飛躍的に向上させると同時に、新しい仲間とのチームビルディングの機会にもなっています。
ーー学生ごとにデータ分析の習熟度は異なると思いますが、日経POS情報をどのように使い分けているのですか。
横山:提供するデータの種類や授業形式を工夫することで、入門から応用までさまざまなレベルに対応しています。例えば、まだExcelの操作方法を学んだばかりの1年生にいきなり大きなデータを渡しても扱いきれません。そこで最初は「お茶」や「炭酸飲料」など特定のカテゴリーに絞り、併売情報などを除いたシンプルな購買情報を1〜2ヶ月分だけ切り出したうえで、そのデータからどのような商品特徴が読み取れるのかを考えてもらいます。先ほど説明したように学年が上がると、より多様で複雑なデータの解析にも挑戦してもらいます。といっても、分析手法そのものを学ぶことが目的ではありません。授業ではマーケティングにおける実践的な思考力を養うことを主眼に課題設定しています。
横山:まだデータに触ったことのない1年生から、比較的高度な分析を行うゼミの演習まで、私の担当する多くの講義で日経POS情報を取り入れています。
まず1年生には、データ分析の基礎を学ぶ講義を必修科目として学んでもらっています。ここで基礎的なデータリテラシーを身に付け、慣れてきたら日経POS情報の購買データを使ったグループワークに臨みます。2年次に進むとProject-Based Learning (PBL:課題解決型学習)を取り入れた授業が始まります。ここでは週次集計データや、より高度な併売分析が可能なレシートデータなどをもとに、マーケティング的な観点から現状分析や課題解決を議論します。3年次でも継続してゼミの演習に日経POS情報を活用。さらに複数のゼミと共同で、日経POS情報を活用したデータ分析コンペも実施しています。これはデータを渡して50時間で分析しプレゼン資料を作成するというトライアルで、スキルを飛躍的に向上させると同時に、新しい仲間とのチームビルディングの機会にもなっています。
ーー学生ごとにデータ分析の習熟度は異なると思いますが、日経POS情報をどのように使い分けているのですか。
横山:提供するデータの種類や授業形式を工夫することで、入門から応用までさまざまなレベルに対応しています。例えば、まだExcelの操作方法を学んだばかりの1年生にいきなり大きなデータを渡しても扱いきれません。そこで最初は「お茶」や「炭酸飲料」など特定のカテゴリーに絞り、併売情報などを除いたシンプルな購買情報を1〜2ヶ月分だけ切り出したうえで、そのデータからどのような商品特徴が読み取れるのかを考えてもらいます。先ほど説明したように学年が上がると、より多様で複雑なデータの解析にも挑戦してもらいます。といっても、分析手法そのものを学ぶことが目的ではありません。授業ではマーケティングにおける実践的な思考力を養うことを主眼に課題設定しています。
仮説どおりにならない「生きたデータ」に向き合い、自ら問いを立てる
一一実際の購買データを使った授業だからこその学びとはどのような点にありますか。
横山:「生きたデータ」は仮説どおりにならないことも多く、そこに面白さがあると考えています。例えばある班が「板チョコ」における競合ブランドの売上を比較したところ、ほとんど売上に差が出ませんでした。学生たちは「差がある」という前提で分析したため戸惑っていましたが、現実世界では期待に反する結果が出ることはしばしばあります。また別の班がアイドルグループとコラボしたお菓子のキャンペーンを分析したところ、大規模な販促にも関わらずコンビニでのお菓子の売上が下がっていることを発見しました。そこで学生たちは「コンビニの購買層は男性が多く、アイドルのパッケージを手に取るのを避けたのではないか」といった議論を発展させていました。データから思いどおりにはいかない結果が導かれたとき、「なぜこうなった?」と自ら考えていく。そのプロセスを重視しています。
ーーデータを生かしたマーケティングを学ぶうえで、工夫した点はありますか。
横山:「データからマーケティング施策を考える」というテーマを与えると、学生が自説に都合の良いデータを探してしまいます。それでは、「KKD」に頼る経営と変わりません。そこで授業では「データからマーケティングに活用できそうな事柄を導き出す」というように、デー夕と真摯に向き合わざるを得ない課題設定にしています。そこで仮説に反した結果が出たとき、意欲のある学生はその背景を探るために、例えば自ら気象庁のサイトから気温のデータを取ってきたりと、一歩踏み込んで考えます。データを足がかりに自ら問いを立て、意見を言える学生はやはり優秀ですし、大きく成長していきます。
ーーデータを用いた授業に対して、評価が変わってきていると感じますか。
横山:やはり、就職活動でデータを扱える学生の評価が大きく変わってきています。10年ほど前は「データ分析ができる」と言うとエンジニア職と勘違いされることも多かったのですが、今ではデータと向き合えるマーケターというと企業からの反応が非常に良く、学生がアピールできる強力な武器になっています。
横山:「生きたデータ」は仮説どおりにならないことも多く、そこに面白さがあると考えています。例えばある班が「板チョコ」における競合ブランドの売上を比較したところ、ほとんど売上に差が出ませんでした。学生たちは「差がある」という前提で分析したため戸惑っていましたが、現実世界では期待に反する結果が出ることはしばしばあります。また別の班がアイドルグループとコラボしたお菓子のキャンペーンを分析したところ、大規模な販促にも関わらずコンビニでのお菓子の売上が下がっていることを発見しました。そこで学生たちは「コンビニの購買層は男性が多く、アイドルのパッケージを手に取るのを避けたのではないか」といった議論を発展させていました。データから思いどおりにはいかない結果が導かれたとき、「なぜこうなった?」と自ら考えていく。そのプロセスを重視しています。
ーーデータを生かしたマーケティングを学ぶうえで、工夫した点はありますか。
横山:「データからマーケティング施策を考える」というテーマを与えると、学生が自説に都合の良いデータを探してしまいます。それでは、「KKD」に頼る経営と変わりません。そこで授業では「データからマーケティングに活用できそうな事柄を導き出す」というように、デー夕と真摯に向き合わざるを得ない課題設定にしています。そこで仮説に反した結果が出たとき、意欲のある学生はその背景を探るために、例えば自ら気象庁のサイトから気温のデータを取ってきたりと、一歩踏み込んで考えます。データを足がかりに自ら問いを立て、意見を言える学生はやはり優秀ですし、大きく成長していきます。
ーーデータを用いた授業に対して、評価が変わってきていると感じますか。
横山:やはり、就職活動でデータを扱える学生の評価が大きく変わってきています。10年ほど前は「データ分析ができる」と言うとエンジニア職と勘違いされることも多かったのですが、今ではデータと向き合えるマーケターというと企業からの反応が非常に良く、学生がアピールできる強力な武器になっています。
今後の展望
AIの提示する答えをうのみにせず、批判的に解釈する力につながる
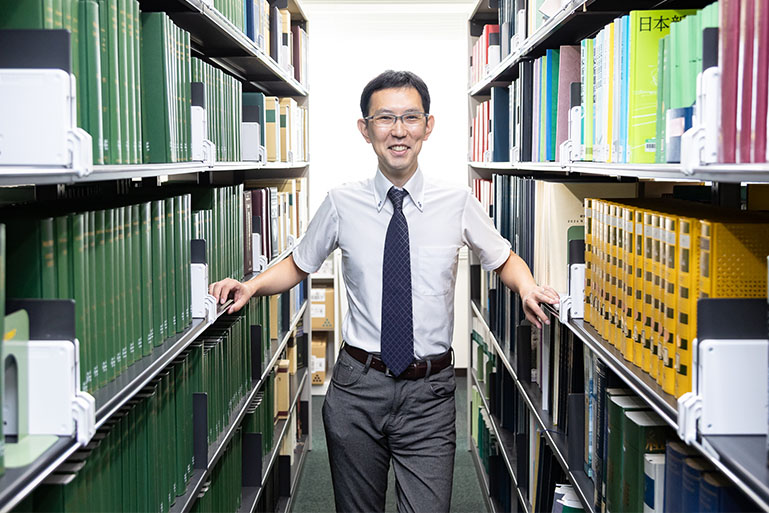
ーーAI時代における実践的なデータ教育の意義をどうお考えですか。
横山:今後、分析そのものはAIが代行する部分が増えてくると思います。しかしAIの分析結果を見て、意思決定を下す、その最後の責任は必ず人間が負います。そこで重要になるのが、AIの導き出した結果をうのみにせず、批判的にデータを解釈する力です。私たちの授業は、まさにその訓練と言えるでしょう。データに振り回されるのではなく、自らの目的意識を持ってデータを「使いこなす」人材、それこそが私たちが育てたい人物像であり、社会が求める人材でもあります。日経POS情報を使った実践的な学びは、そのための土台作りになっていると確信しています。
横山:今後、分析そのものはAIが代行する部分が増えてくると思います。しかしAIの分析結果を見て、意思決定を下す、その最後の責任は必ず人間が負います。そこで重要になるのが、AIの導き出した結果をうのみにせず、批判的にデータを解釈する力です。私たちの授業は、まさにその訓練と言えるでしょう。データに振り回されるのではなく、自らの目的意識を持ってデータを「使いこなす」人材、それこそが私たちが育てたい人物像であり、社会が求める人材でもあります。日経POS情報を使った実践的な学びは、そのための土台作りになっていると確信しています。